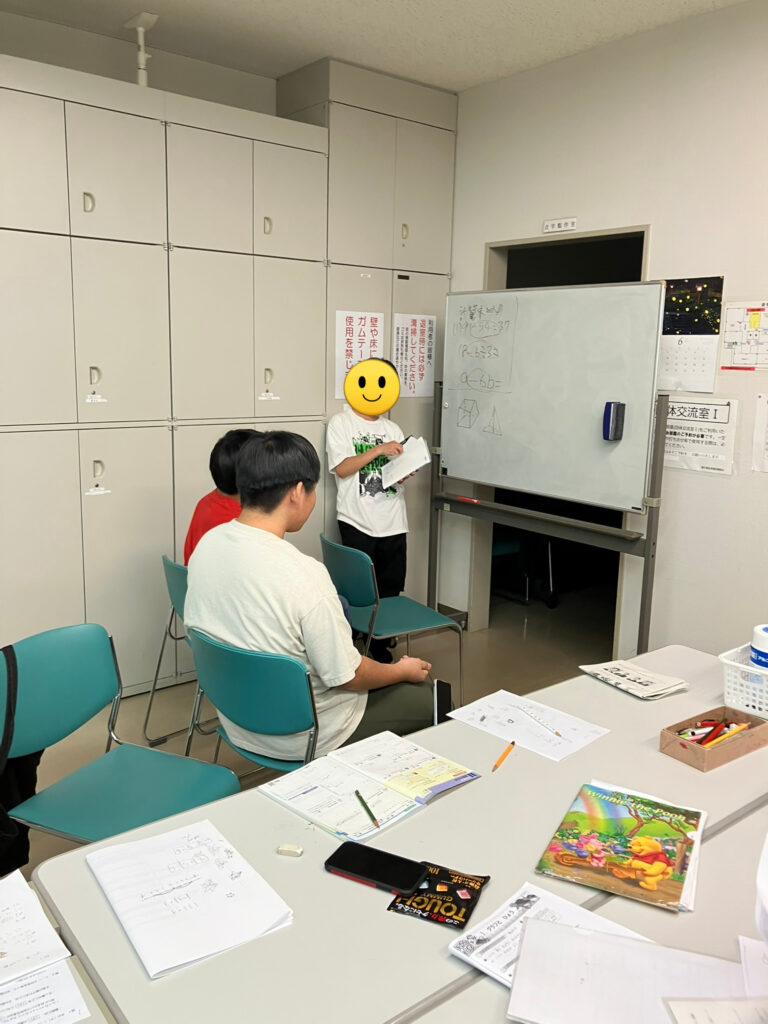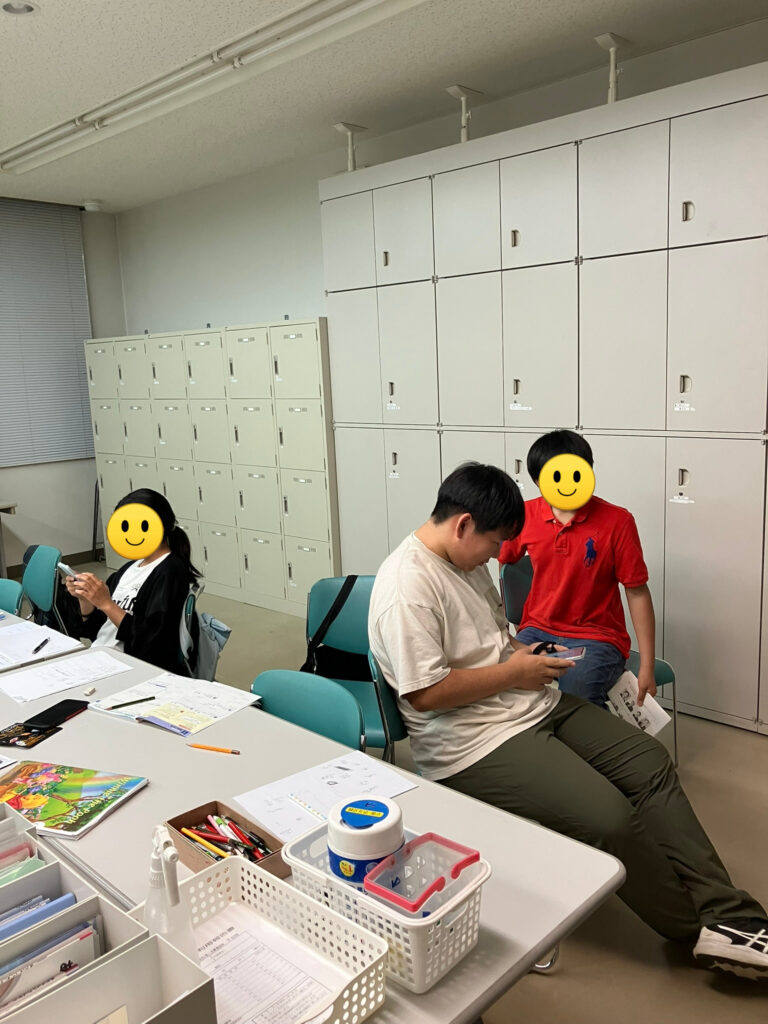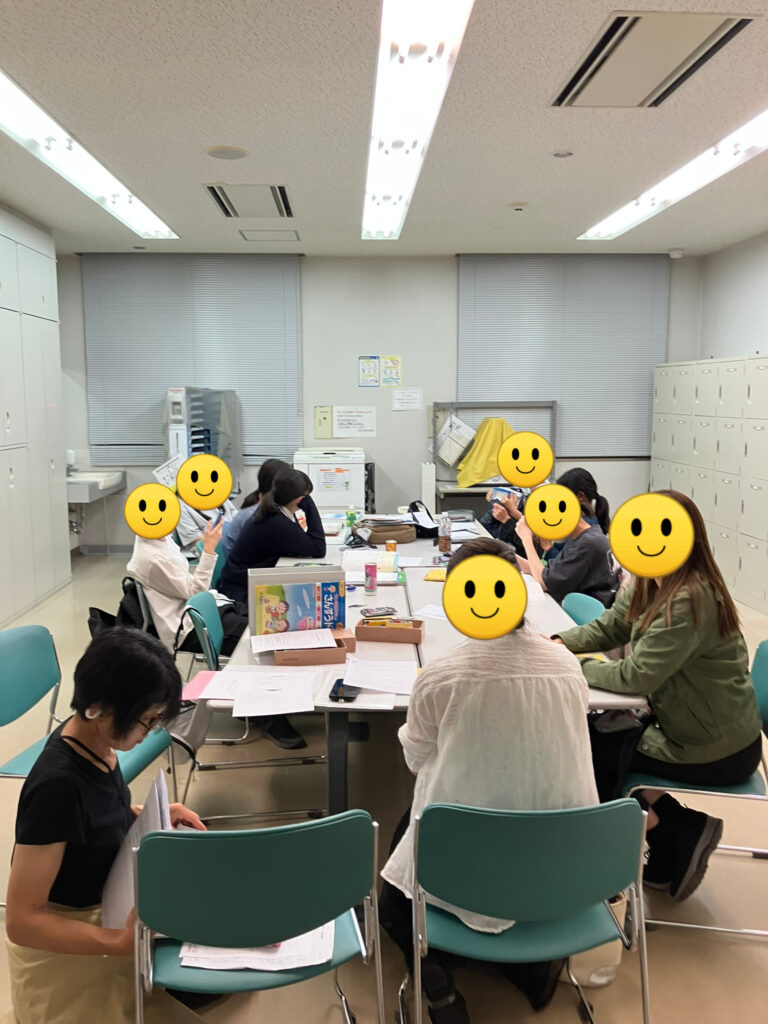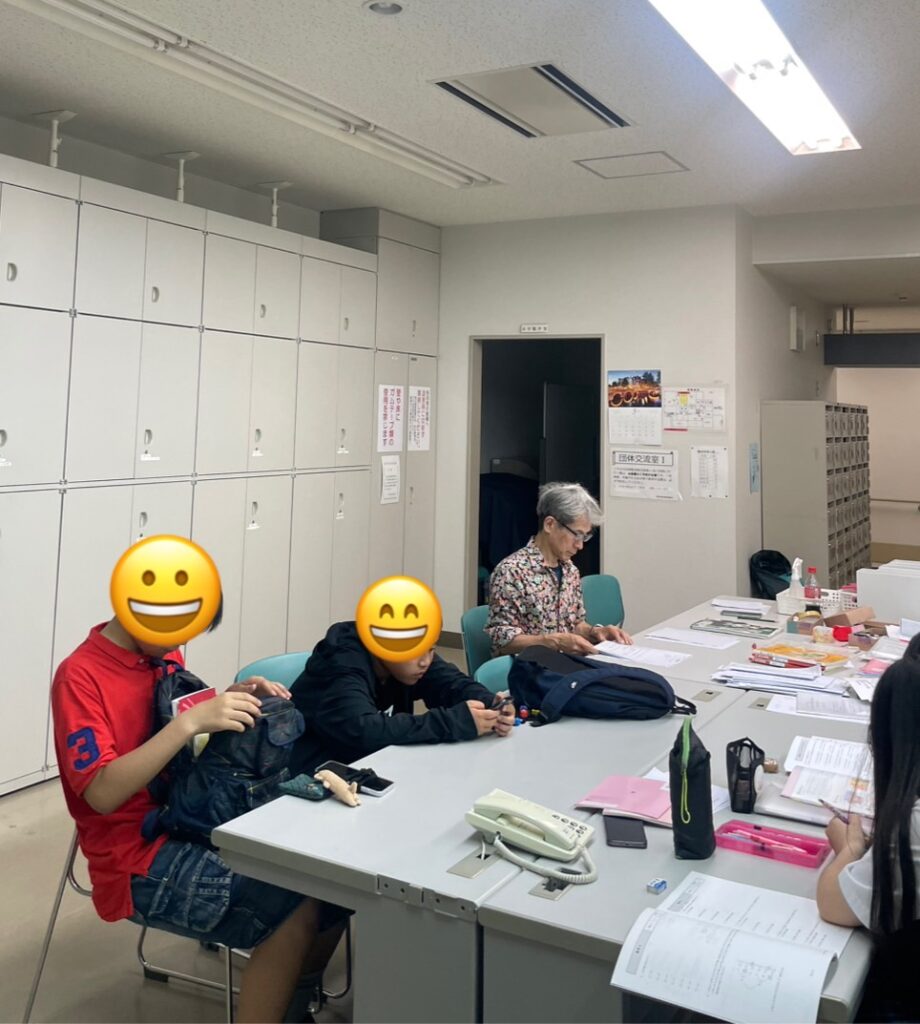6月12日はてらこやの日でした。子ども食堂も開催されていて、何人かはごはんを食べに行っていたようです。
中学生の中間テストは学校ごとに少しずつ時期がずれているので、既に終わって結果が戻ってきている子からこれからの子までさまざまです。はた目には試験が終わった子とこれからの子の区別はつきにくいかもしれません。試験前だからといって急いで対策しようという感じでもないようなので。これから試験の子はテキストの問題を、終わった子はそれぞれですが、塾の課題をやっている子もいました。
高校生はいつもの2人が来てくれました。学校の社会や数学の課題をやっていました。一人の子は近々大学の見学に行く予定があるそうです。そろそろ進路を決める時期に来ているようです。よく考えて悩んで進路を決めてほしいと思います。
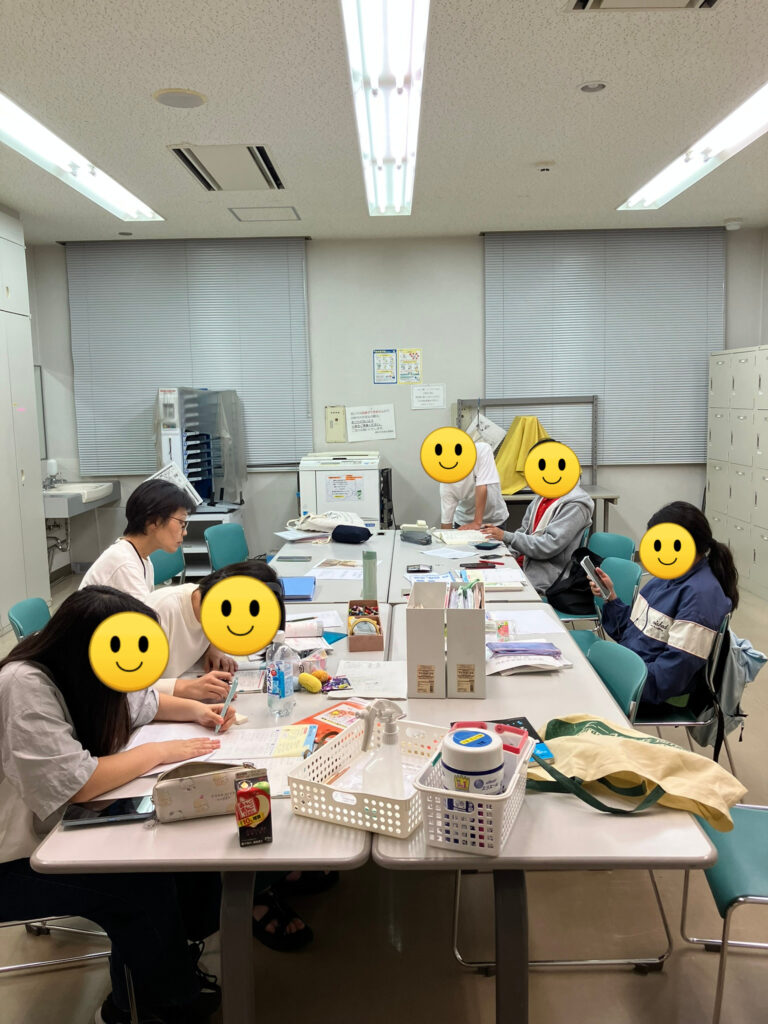
高校生が進路を決める時期になってきました。まだ将来について具体的な希望や方向性が見つかっていないようで、迷いながら考えている様子です。今はいろいろなことが学べる大学があり、知らないだけでびっくりするような大学もあります。いわゆる基礎学問を学ぶ大学だけではなく、環境・エネルギー、デザイン・アート、地方創生・観光、プログラミング・AI・ゲームなど今までは、なっかた内容を扱っている大学や学部が増えています。さらに、受験方法も多様化しているので、ぜひ時間をかけてよく調べたり、実際に見学に行ったりして、自分の目で確かめながら選んでほしいと思います。
今回の選択が、将来に直接つながるものでなくても構わないと私は思っています。いろいろな経験をして、時には失敗したり、やり直したり、試行錯誤を重ねる中で、少しずつ自分の進む道を見つけていければ、それで十分だと思います。