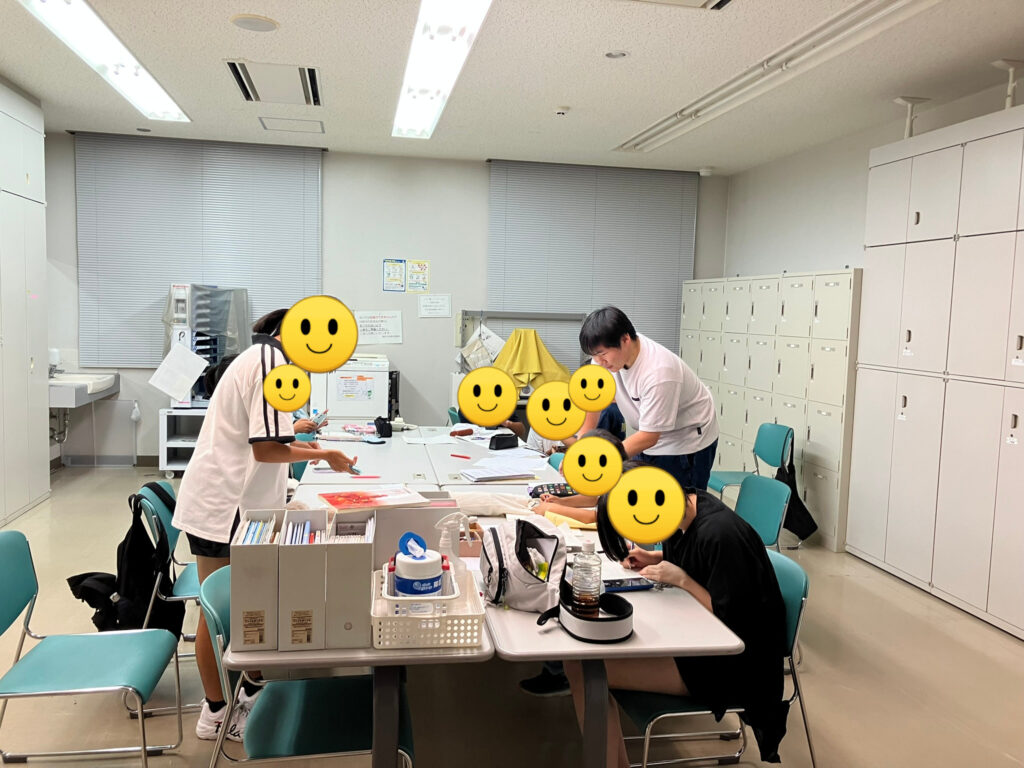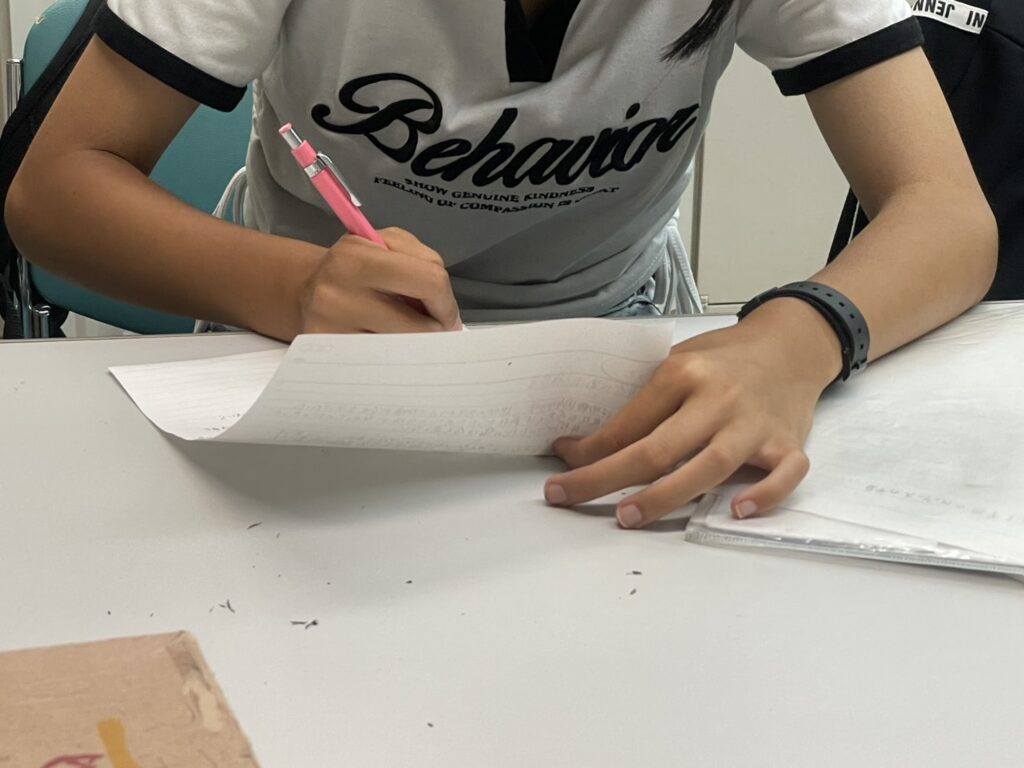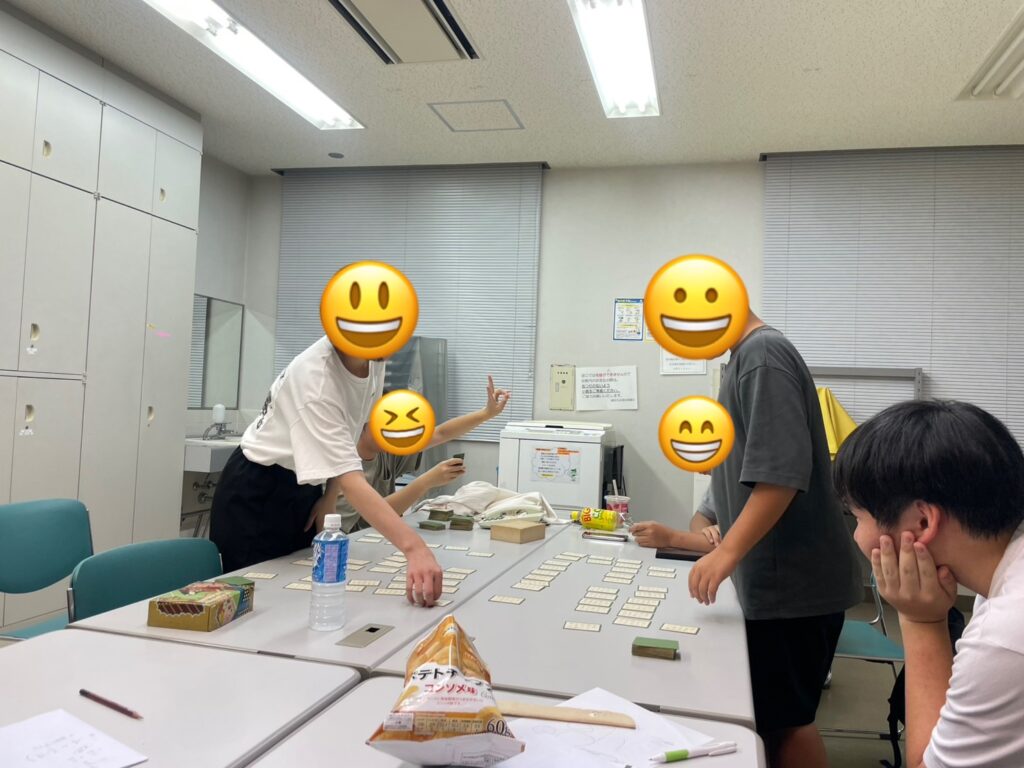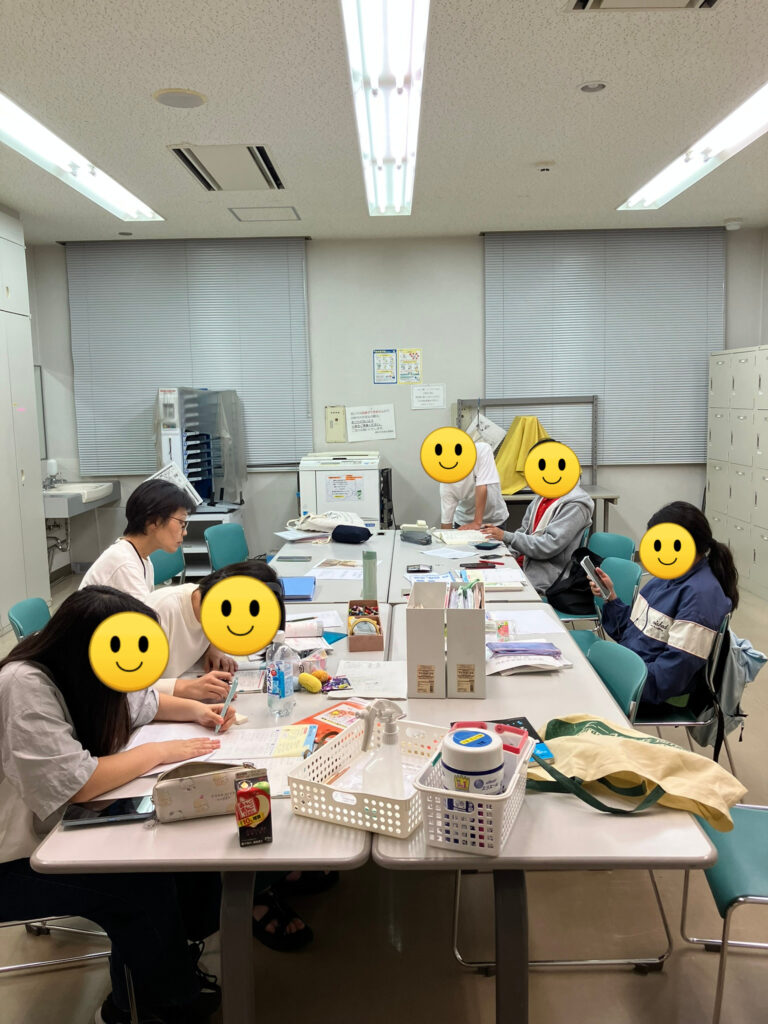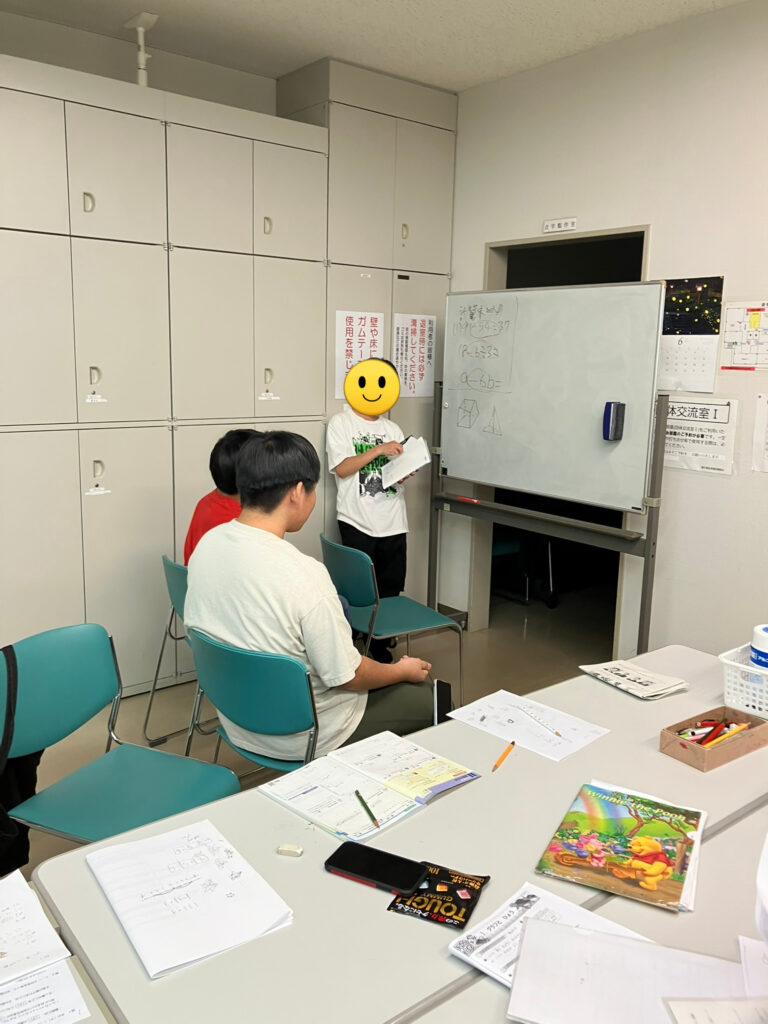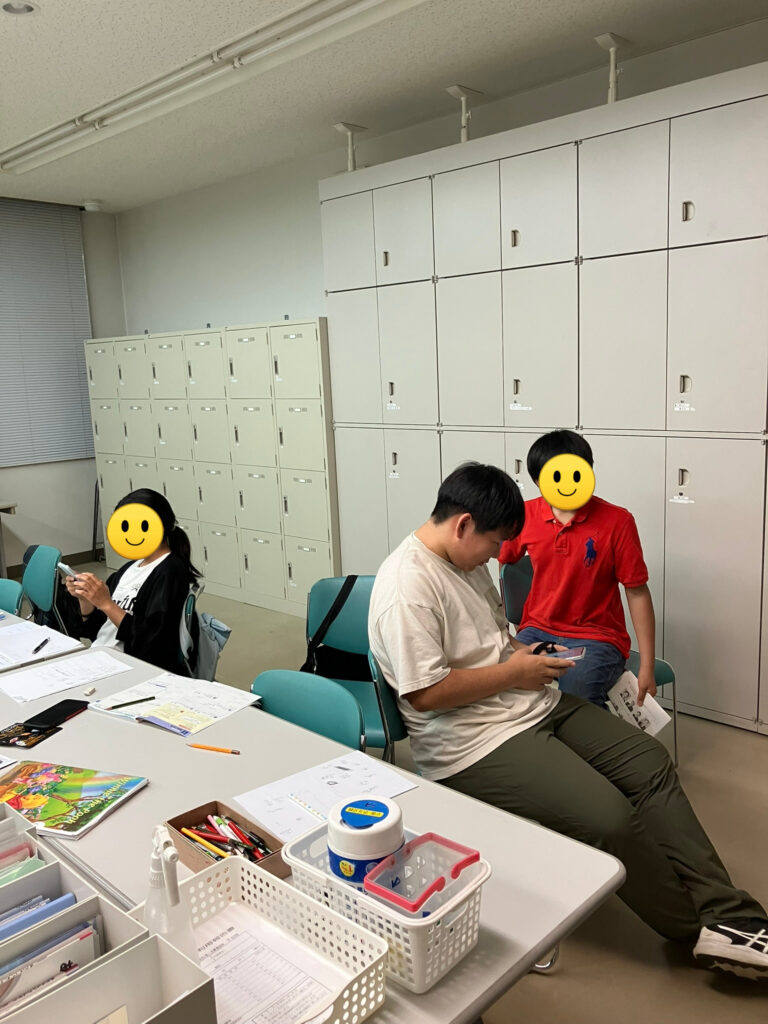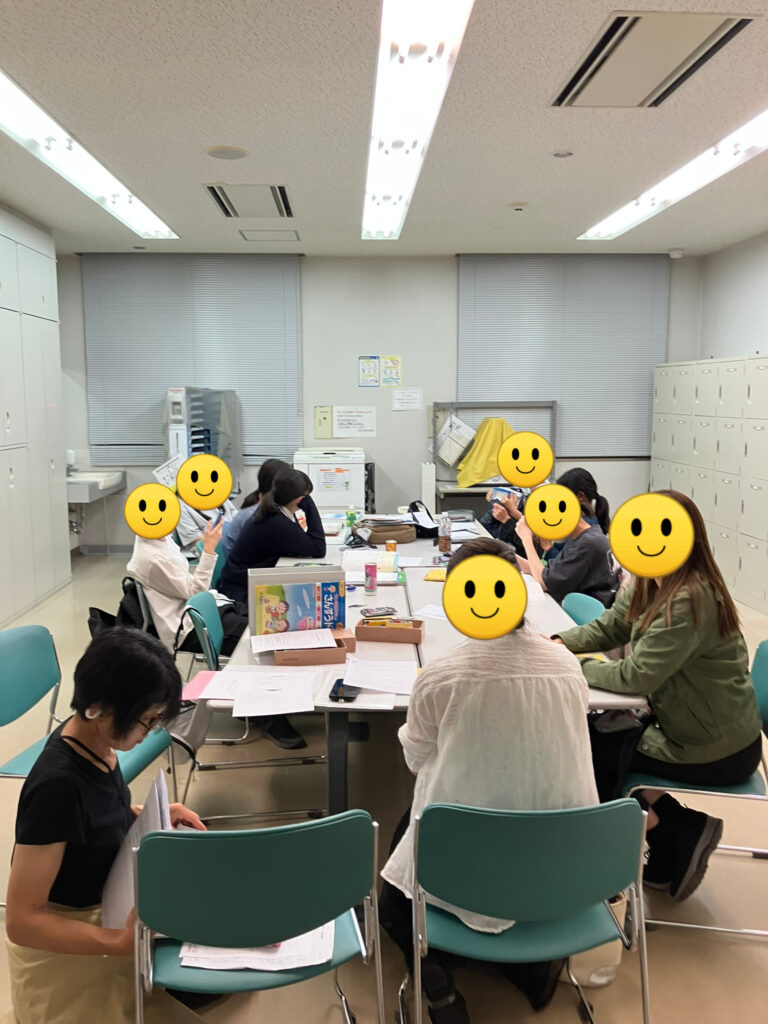7月31日はてらこやの日でした。花火の日でした。6時30分に集合、みんなで会場の公園に移動する予定でしたが、結構みんなバラバラにやってきました。早く来た子もいれば、連絡して直接会場に来ることが分かった子、移動の途中で合流した子等々、てらこやらしいといえばそうかもしれません。
この時期は7時くらいはまだまだ明るいので、花火をするにはまだ少早すぎます。いつもてらこやに来てくれる高校生の子たちは別件の用事があるので来れない、と言っていたにも関わらず、花火が始まる前に公園に寄ってくれました。せっかくなので、少し明るいけどちょっとだけ花火やって行きました。その子たちが去った後、入れ違いで同級生の子が一人来てくれました。もう少し早ければ会えたんだけどな。
まだ少し早いかとか言いながら始めると、薄暮での花火を意外とよいものです。毎年のことですが、ろうそくの火が何度も消えて、チャッカマンで付け直すのが大人たちの仕事です。忙しい・・・。今年は「ターボ式」というライターを100均で買ったのですが、名前ほどでもない感じです。子どもたちは着々と自分の手持ち花火を消化してゆきます。なぜかマシュマロを買ってきて、花火そっちのけで焼いて食べている子もいます。・・・というか、そのうちみんなもらって焼いている・・・。
最後は吹き出し花火12連発です。「火を着けたい人!」を募ると大きい子がいやがったり、小さい子たちがやりたがったり。今年も無事終えることができました。


今回の花火大会では、中学生に対して、言いたいことをぐっとこらえる、場面が何度かありました。始まってすぐ、「コンビニにマシュマロを買いに行きたい」と言い出したときです。頭の中では「今日は花火をやりに来たんだよ」「余計なものは買わないでね」「すぐに帰ってくるんだよ」 そして、そもそも「今、買いに行くってどうなの?」とも思いましたが、買ってくることを許可しました。
しばらくして、なかなか帰ってこないので迎えに行こうとすると、楽しそうにのんびりと帰ってきました。思ったよりも多く買ってきたので、みんなと一緒にやろうとしているのかな?と様子を見つつも、まずは「遅いよ、何してたの?」「自分たちだけで食べないで、みんなにもあげるんだよ」「花火が終わってからね」などなど、学校だったらきっと口にしているような言葉が、次から次へと湧いてきましたがぐっとこらえていました。
しばらくすると、気づけば、花火よりもマシュマロを焼いている子が多いくらいに、みんなでワイワイ楽しそうに焼いていました。 そして、マシュマロがなくなると自然と花火を始まり、最後は全員で吹き出し花火を眺めて楽しく終了。終始楽しそうな雰囲気が流れ、みんなの笑顔がとても印象的でした。余計な口出しをせず、ぐっと堪えてよかった。そして、子どもたちを信じてよかったと、心から思いました。